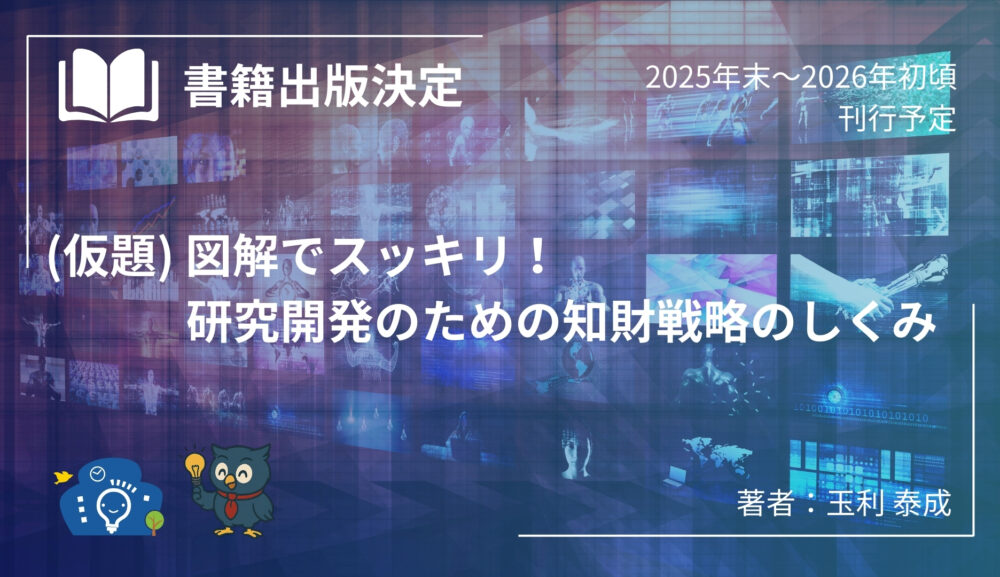いつも知財の楽校のホームページをご覧いただきありがとうございます。
本日は皆さまに重要なお知らせがございます。
この度、知財の楽校 代表の玉利が書籍を出版することになりました!
既に原稿を書き終えており、出版については確定しましたので、この場を借りてお知らせいたします。
※内容は一部変更の可能性がございます。
タイトル:図解でスッキリ!研究開発のための知財戦略の仕組み(仮題)
著者氏名:玉利泰成
出版社 :中央経済社
刊行時期:2025年末~2026年初頃
図解枚数:110枚以上
目次(仮)
第1章 事業・研究開発と知財戦略の繋がり
1-1 研究開発活動を加速する知財戦略
1-1-1 研究開発のステージと無形資産の蓄積
1-1-2 研究開発のステージアップと事業ファイブフォースの強まり
1-1-3 研究開発による無形資産を原資にしたテリトリー構築
1-1-4 ナレッジマネジメントによる研究開発の加速
1-1-5 事業のスケーリングに対する研究開発・知財戦略の役割
1-2 ビジネスモデルの実現と知財戦略
1-2-1 そもそもビジネスモデルとは何か
1-2-2 ビジネスモデルと研究開発成果を繋ぐ知財戦略
1-2-3 オープン&クローズドによるビジネスモデルの高解像度化
1-3 攻めと守りの両面で捉える知財戦略
1-3-1 事業領域の陣取り合戦で捉える知財活動
1-3-2 攻めと守りの知財ポートフォリオ
1-3-3 ビジネスモデルと攻守の知財戦略ドメインの符合
第2章 ここだけ押さえる!特許の前提知識
2-1 特許制度とは
2-1-1 特許制度の趣旨と構図
2-1-2 研究開発者と特許制度の関係性
2-2 特許請求の範囲と出願明細書
2-2-1 特許請求の範囲の読み解き方
2-2-2 出願明細書の読み解き方
2-3 特許出願とは
2-3-1 自社特許出願と他社事業との位置関係
2-3-2 自社特許出願の基本的な流れ
2-4 特許審査とは
2-4-1 権利化に要する時間と基本的な流れ
2-4-2 審査でチェックされる代表的な項目
2-5 他社特許対策とは
2-5-1 他社特許対策と自社事業との位置関係
2-5-2 他社特許対策の基本的な流れ
2-6 特許における早さの重要性
2-6-1 特許は早い者勝ちと言われる理由
2-6-2 特許の早い遅いは何を基準に判断されるか
第3章 フレームワークで学ぶ!自社特許ポートフォリオの形成
3-1 特許網構築の意義と全体像
3-1-1 守りと攻めで見る特許網の意義
3-1-2 個と群で高める特許網の価値
3-1-3 事業・開発オプションと特許ポートフォリオ
3-1-4 特許ポートフォリオ形成の全体像と進め方(5W1H)
3-2 「技術」視点の特許ポートフォリオ(What)
3-2-1 特許ポートフォリオの充実化を妨げているファクター
3-2-2 技術と特許を繋ぎ発想を拡げるフレームワーク
3-2-3 技術のカテゴリに着目したPPFのフレームワーク
3-2-4 特許のカテゴリに着目したPPFのフレームワーク
3-3 「時間」視点の特許ポートフォリオ(When)
3-3-1 特許権の存続期間の捉え方
3-3-2 特許権の領域と時間経過に伴う変化
3-3-3 プロダクトライフサイクルと技術のステージアップ
3-3-4 ライフサイクルを想定した特許出願の継ぎ矢
3-3-5 事業フェーズとともに移り行く特許出願の切り口
3-4 「場所」視点の特許ポートフォリオ(Where)
3-4-1 国毎にパッケージ化される特許ポートフォリオ
3-4-2 事業貢献度を想定した権利化国の選び方
3-4-3 各国特許権の効力が及ぶ実施行為の射程
3-4-4 物質/製法特許と販売/生産国の繋がり
3-4-5 権利化国の選定基準となる考慮要素(事業面)
3-4-6 権利化国の選定基準となる考慮要素(特許面)
3-4-7 総合考慮による出願国の決定
3-5 特許網構築の「方法」とアプローチ(How)
3-5-1 特許網構築のジレンマと2つのアプローチ
3-5-2 フォアキャスト型の特許ポートフォリオの組み方
3-5-3 質のポートフォリオで見る個別特許のクライテリア
3-5-4 バックキャスト型の特許ポートフォリオの組み方
第4章 フレームワークで学ぶ!他社特許に対するクリアランス
4-1 他社特許対策の意義と全体像
4-1-1 他社特許権が事業に及ぼす影響
4-1-2 他社特許対策におけるリスク要因
4-1-3 他社特許と自社技術のフェーズで見る対策の相関
4-1-4 他社特許対策の全体像と流れ
4-2 他社特許の「調査」
4-2-1 特許調査の類型とその特徴
4-2-2 侵害予防調査(FTO)とは
4-2-3 無効資料調査とは
4-3 他社特許の「スクリーニング」
4-3-1 自社技術と他社特許の対比方法
4-3-2 他社特許の自社事業への関連性を見極めるポイント
4-3-3 他社特許の権利範囲と侵害有無のグレーゾーン
4-3-4 他社特許スクリーニングのモデルフロー
4-4 他社特許への対策実行「手段」
4-4-1 他社特許対策における4つの代表的な実行手段
4-4-2 特許権の無効化/実施技術による回避
4-4-3 特許権の購入/ライセンス許諾
4-4-4 その他の予備的な対策手段
4-4-5 特許権の無効化手続きの選択肢
4-5 他社特許の「監視」と「管理」
4-5-1 他社特許対策の実行マネジメント
4-5-2 他社特許対策の組織的なリソース配分
4-5-3 群で見通す他社特許対策
4-5-4 監視による対策実行タイミングの見極め方
4-5-5 権利範囲の有効性と対策実行範囲の見極め方
4-5-6 他社特許クリアランスを通して生まれる結束
第5章 ここまで押さえる!特許の基礎知識
5-1 特許要件とは
5-1-1 新規性とその攻略法
5-1-2 進歩性とその攻略法
5-1-3 記載要件とその攻略法
5-2 出願前先行技術調査とは
5-2-1 出願前先行技術調査の全体像と流れ
5-2-2 研究開発フェーズと連動させる出願前先行技術調査
5-3 拒絶対応とは
5-3-1 拒絶理由通知と2つの対応手段
5-3-2 拒絶対応時に押さえるべきポイント
5-3-3 拒絶対応時の方針の落とし込み方
5-4 特許維持管理とは
5-4-1 特許権の維持に要する費用
5-4-2 事業環境を踏まえた特許の棚卸と維持管理
5-5 ノウハウ秘匿とは
5-5-1 発明の保護手段の選択肢とその特徴
5-5-2 特許出願と秘匿化の両天秤
5-5-3 特許出願>秘匿化の重み付け
5-5-4 秘匿化>特許出願の重み付け
第6章 研究開発人材と知財人材の共鳴
6-1 専門人材の共創関係
6-2 研究開発人材と知財人材で生み出せるシナジー
書籍の原稿から「はじめに」だけ特別に先行公開いたします!今後も最新情報や内容の一部をお知らせしていきますので、ご興味のある方は「メルマガ」をご登録ください。
はじめに
本書は、「研究開発のための知財戦略」について綴った実践書です。
技術やナレッジが企業競争力の源泉となる時代、研究開発活動と知的財産の関係はより密接で不可分なものとなっています。そうした現場の実態をふまえ、知財を研究開発と同一線上にある“戦略の手段”として捉え直すこと。それが本書の最大のテーマです。特徴は以下の5つが挙げられます。
(1)研究開発と一体で知財戦略を考える視点を大切にしました。事業戦略の実現を共通のミッションに置き、全編を通じて、研究開発現場に根差した視点を意識し解説しています。
(2)図解によるフレームワーク化を重視しました。知財戦略はどうしても抽象的で、机上で議論されがちです。だからこそ、技術や事業の文脈に引き寄せながら、実践へとつなげる“思考プロセス”として可視化しています。
(3)研究開発人材と知財実務人材の共通言語を創るという姿勢で書きました。よくある“知財実務家目線の入門書”ではなく、研究開発と知財の主観・客観をすり合わせ、その接点にある「共有知識」を築くための構成にしています。
(4)実務の必要なシーンですぐに開き直して使える利便性を重視しています。章ごとに体系的なストーリーラインはありますが、項目別でも独立して読みやすいコンパクトな構成にしてあります。
(5)あえて題材を研究開発の成果として代表的な「技術と特許」の関係性に絞り、その考え方を丁寧に掘り下げました。もちろん、知財権には意匠、商標、著作など多様なカテゴリがあり、近年では無形資産全体を視野に入れた“知財ミックス”の重要性も高まっています。一方で、知財戦略の本質はカテゴリに依存しない共通原理が多く、考え方の軸をまず体得することを目標にしました。
本書を執筆するにあたって、筆者自身の経験も大きな支えとなりました。
私は新卒で事業会社の知財部門に入り、間もなくして研究開発現場に常駐し、研究者のすぐ隣で知財実務に携わることになりました。その後、新規事業部門の立ち上げに際し、知財戦略機能の創設メンバーとして異動、さらに現在は、ディープテック系のスタートアップにフィールドを移し、経営層や社会実装チーム、研究者と日々議論を交わしながら、実際の事業と一体となって知財戦略にトライしています。
このような現場感に触れる日常だからこそ、理想論ではなく、リアルな実践論として、知財戦略のあり方を解きほぐしてみたいと思いました。
知財は、特定の専門職だけが扱う領域ではなくなりつつあります。研究開発者も、事業開発者も、そして知財担当者も・・・それぞれの役割を担いながら、技術の価値を社会に届けていく仲間です。本書が、そんな仲間同士をつなぐ“共通言語”となり、対話と共創のきっかけとなることを願っています。
技術に懸ける想いを、未来の社会を支える事業の創出へと繋げるために――
「図解でスッキリ!研究開発のための知財戦略のしくみ」を、読者の皆さまに届けに行きます。
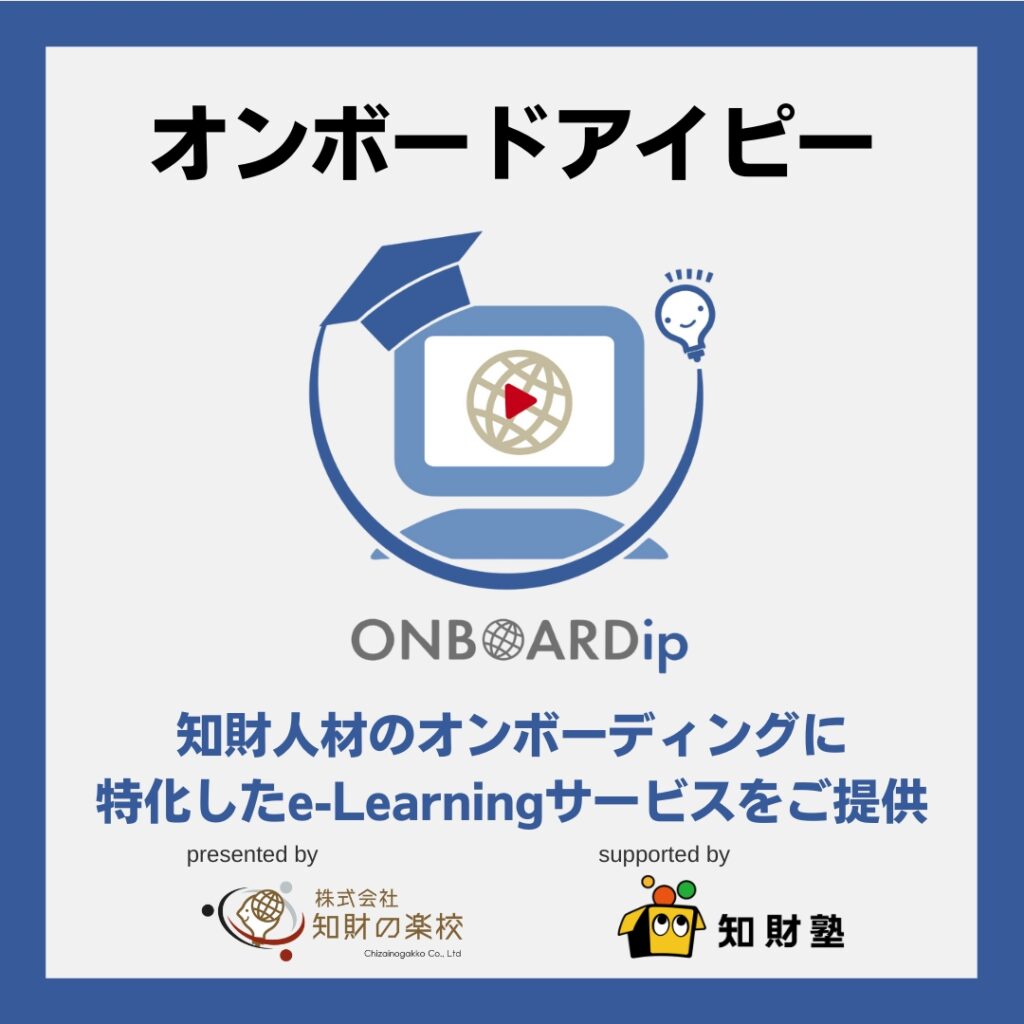
オンボードアイピー
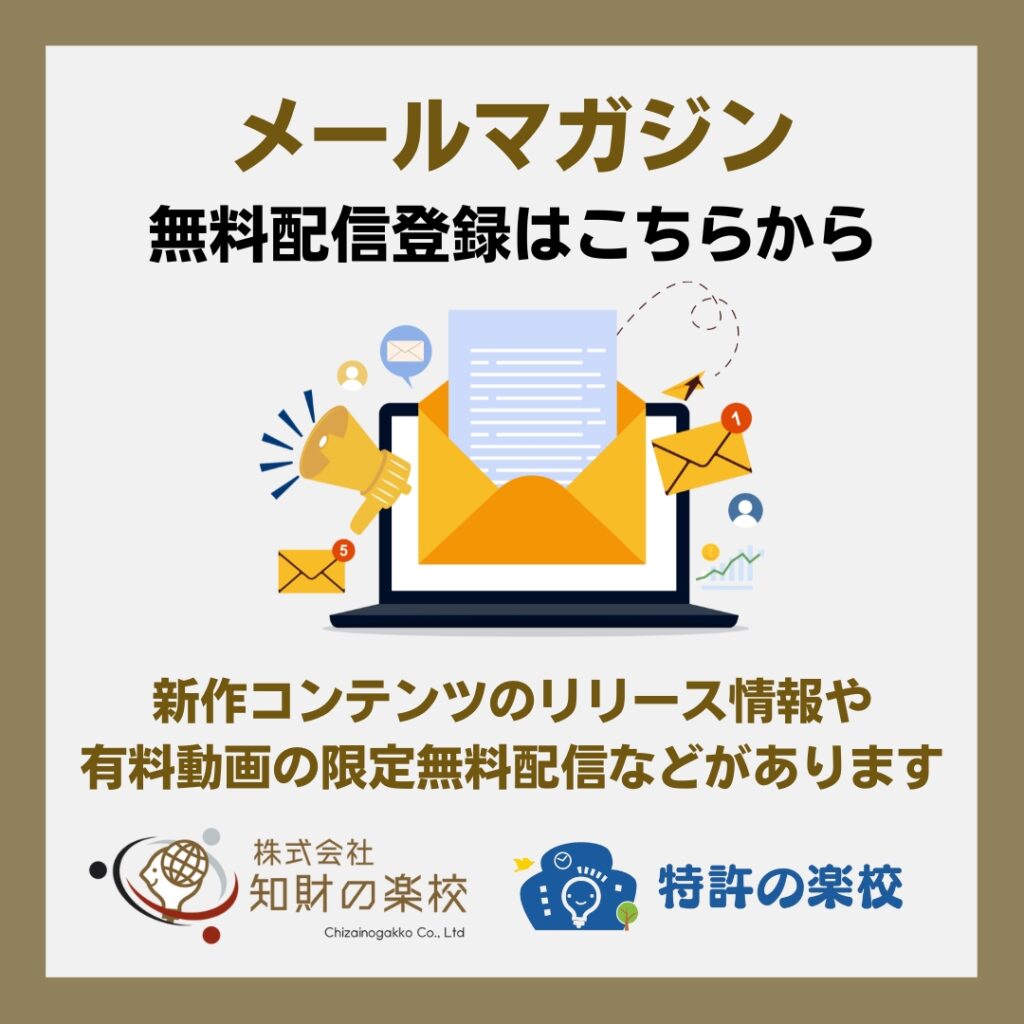
知財の楽校 公式メールマガジン